【筋膜螺旋の生理学】まとめ
■ 筋膜対角線と運動方式
-
**直線的な筋線維(長軸方向)**は「筋膜配列」に、螺旋的な筋線維は「筋膜螺旋」に関与。
-
筋線維自体は一方向にしか働けないが、筋膜のつながりにより多様な運動に関与可能。
■ 筋膜螺旋と反射活動
-
「筋膜対角線」と「筋膜螺旋」は異なる運動方式:
-
1つの分節で2つの筋膜単位が同時に活性化。
-
四肢や体幹の複数の筋膜単位が同時活性化。
-
-
1つの螺旋は、隣接する2分節で反対方向の運動を同時に活性化。
-
脊髄反射(伸張反射)が運動協調を支えるが、螺旋状コラーゲン構造により反射なしでも周期的活動が可能とする動物実験結果も。
■ 筋膜螺旋と運動の活性化
-
筋膜螺旋=湾曲・屈曲・回旋に優れた柔軟な構造。
-
直線構造(長軸配列)は安定性・強度重視だが、柔軟性は低い。
-
神経調整:
-
CC(Contractile Chain):筋腹上に位置し、筋紡錘を介して1分節内で他と同期。
-
CF(Contractile Field):腱や支帯上に位置し、ゴルジ腱器官を介して3つの筋膜単位を制御。
-
-
自由な動作には螺旋組織が介入し、力が求められる動作には直線配列(筋膜配列)が活性化。
|
|



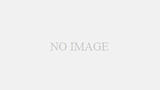
コメント