🦵下肢の筋膜配列とは?
筋膜マニピュレーション理論における下肢の運動は、6つの方向性(前方・後方・内方・外方・内旋・外旋)に分けて理解されます。各筋群は独立して存在するわけではなく、筋膜を通じて**連続した運動配列(モーションユニット)**を形成しています。
▶️ 下肢の前方運動配列
-
主な構成筋:前脛骨筋、長趾伸筋、長母趾伸筋、短母趾伸筋、大腿四頭筋、腸腰筋
-
特徴:
-
足関節の背屈や足趾の伸展を担う。
-
大腿四頭筋は下腿筋膜を近位方向に、前脛骨筋らは遠位方向に牽引。
-
筋膜は、上からも下からも引っ張られる二方向のテンション構造になっている。
-
🔙 下肢の後方運動配列
-
主な構成筋:下腿三頭筋、小趾外転筋、半腱様筋、半膜様筋、大殿筋、脊柱起立筋
-
特徴:
-
足関節の底屈(蹴りだし)と股関節の伸展に関与。
-
足底腱膜~アキレス腱~大腿後面筋膜~骨盤靭帯までが連続して張力を伝達。
-
歩行時、蹴りだしの瞬間に最大のテンションがかかる構造。
-
🔽 下肢の内方運動配列
-
主な構成筋:底側骨間筋、母趾内転筋、小趾対立筋、長趾屈筋、薄筋、内転筋群
-
特徴:
-
**足趾や下肢を体の中心へ引き寄せる(内転)**運動に対応。
-
足底筋膜と膝窩筋膜を通じて、足から股関節まで内側の安定性を支える。
-
薄筋や内転筋は筋膜を通じて骨盤・大腿・膝関節の内側安定性に寄与。
-
🔼 下肢の外方運動配列
-
主な構成筋:背側骨間筋、第三腓骨筋、大腿筋膜張筋、大殿筋、中殿筋
-
特徴:
-
足趾や下肢を体の外側に開く(外転)動作に関与。
-
腸脛靭帯を通じて、膝関節外側と骨盤外側の安定性を連動して支える。
-
外方配列は筋線維が少ないため、足首の捻挫リスクが高くなる。
-
🔄 下肢の内旋運動配列
-
主な構成筋:母趾外転筋、前脛骨筋、後脛骨筋、縫工筋、大腿筋膜張筋、大内転筋
-
特徴:
-
前足部や股関節を内側に捻る動きに関与。
-
開放連鎖では股関節、閉鎖連鎖では骨盤が内旋する。
-
脳は骨盤と下肢の筋膜単位を**「ひとつのユニット」として認識**している。
-
🔁 下肢の外旋運動配列
-
主な構成筋:短趾伸筋、長腓骨筋、短腓骨筋、大腿二頭筋、梨状筋、中・小殿筋
-
特徴:
-
足趾や前足部を外側に捻る動作に対応。
-
腓骨筋から大腿外側筋膜、さらに股関節外旋筋群まで連続した筋膜ラインが存在。
-
中・小殿筋は、骨盤の外旋と股関節の安定性を同時に担う張筋となる。
-
|
|



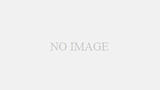
コメント