【筋膜マニュピレーション理論】筋膜配列の生理学と姿勢・感覚の関係
筋膜マニュピレーションでは、「筋膜」が単なる組織のつながりではなく、運動・姿勢・感覚・痛みに深く関わる重要な生理学的構造とされています。
今回は、筋膜配列の生理的な働きにフォーカスして解説します。
✅ 筋膜配列は“動き”と“感覚”の媒介役
筋膜配列には以下のような機能が備わっています:
-
わずかな伸張刺激を感じ取る感覚受容器の存在
-
各配列が特定の運動方向に反応する構造
-
身体姿勢を安定させる張力構造
-
筋膜の異常(高密度化)を“姿勢の代償”でカバーする能力
つまり、筋膜配列は動きと感覚の橋渡し役であり、姿勢の調整装置でもあるのです。
🧠 筋膜配列の張力と感覚入力のしくみ
筋膜には、筋や腱・関節から伸びた神経受容器が多数埋め込まれています。
これらは、筋膜に“基底張力”があるときに初めて活性化されます。
この張力を提供しているのが、筋から筋膜上へと伸びる筋線維です。
▶️ 筋膜に張力を与える感覚受容器(代表例)
| 種別 | 名称 | 反応する刺激 |
|---|---|---|
| 筋受容器 | 筋紡錘 | 伸張 |
| 〃 | 腱紡錘 | 伸張 |
| 〃 | パチニ小体 | 張力変化 |
| 〃 | 自由神経終末 | 張力/機械刺激 |
| 関節受容器 | ルフィニ小体 | 基底伸張 |
| 〃 | ゴルジ・マッツォーニ小体 | 最大伸張 |
| 〃 | パチニ小体 | 運動の開始/終了 |
👉 これら受容器の情報により、脳は身体の運動方向や位置を正確に把握できます。
🧍♀️ 姿勢と筋膜:二重の運動プログラムとは?
私たちが運動を行うとき、脳内では以下の2種類の運動プログラムが同時に作動しています。
-
目的運動:手を挙げる、歩く、ジャンプなど
-
姿勢調整:動作に伴う重心の安定化や反作用への対応
この**「運動+姿勢」**の制御を完結させるのが、筋膜配列です。
また、これには以下の2つの感覚入力(求心路)が対応しています:
| 感覚の種類 | 役割 |
|---|---|
| 静的固有感覚 | 姿勢や関節の静的な位置認知 |
| 動的固有感覚 | 動きや変化のスピードの認知 |
🧵 筋膜の構造と姿勢制御の違い
筋膜には以下の2種類のコラーゲン線維が存在し、それぞれ役割が異なります。
| 線維の種類 | 機能 |
|---|---|
| 長軸方向のコラーゲン線維 | 姿勢制御に関与 |
| 螺旋状コラーゲン線維 | **動きの調整(協調運動)**に関与 |
このように、筋膜は静止時の支持と動作時の協調、両方の機能を支えているのです。
🧍♂️ 姿勢の“代償”としての筋膜の働き
筋膜には、姿勢の崩れを代償するメカニズムも備わっています。
-
骨格は身体を支えるが、アライメント(整列)を維持する力はない
-
筋膜は全身の骨格・筋・関節に接続しており、全体の整合性を担保
🔁 姿勢代償のしくみ
-
筋膜の一部に高密度化(癒着・硬化)が生じる
-
神経受容器が異常な張力に反応し、痛みを発生
-
身体は姿勢パターンを変化(代償)させて、痛みを回避
👉 これは一時的な適応であり、筋膜の機能に根本的な回復を与えるわけではありません。
✍️ まとめ:筋膜は“動くための感覚地図”
-
筋膜配列は、張力と受容器によって身体の位置と動きを感知するセンサー網
-
動作時には、目的運動と姿勢制御の2系統の神経経路と連携
-
姿勢の崩れや筋膜の異常には代償機構が作動し、痛みを回避する
-
筋膜は構造的にも、動的にも、感覚的にも“全身をつなぐ”役割を持つ
|
|



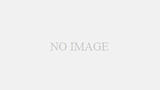
コメント