筋膜マニュピレーションとは?
筋膜単位の機能障害の本質は、CC(協調中心)の高密度化にあります。これは筋膜が本来持つ「伸びる」「適応する」性質を失い、深層筋の張力にうまく対応できなくなった状態を指します。
筋膜が痛みを引き起こすメカニズム
実は、私たちが感じる慢性的な痛みや不調の多くは筋膜由来。筋肉・骨・神経・血管といった他の組織と比較しても、筋膜は最も神経支配が豊富な組織であり、痛みに関与しやすいのです。
✅ 筋膜の特性
-
弾力性があるが、無限ではない(=限界を超えると痛みや運動障害へ)
-
神経受容器が集中しており、協調・認知の中枢(CC)とリンク
-
繰り返しのストレスで粘性変化を起こし、高密度化につながる
高密度化が起きるプロセス
| 要因 | 起こること | 結果 |
|---|---|---|
| 繰り返しの牽引・ストレス | 筋膜基質の変性 | 高密度化(=可動性・順応性の低下) |
| 捻挫や外傷 | 線維芽細胞が過剰に活性化 | 硬く不均一なコラーゲン配列 |
| 姿勢不良 | 一部の筋膜に持続的ストレス | 緩やかな線維化・慢性痛 |
| 加齢 | 弾性低下 | ただし左右均等なら問題は起きにくい |
マニュピレーションの意義
マニュピレーションとは、高密度化したCCに対して摩擦刺激を与え、熱を発生させ、再構築プロセスを促す治療法です。これにより、以下のような変化が期待できます:
-
粘性の調整 → 可動性と順応性の回復
-
適度な炎症 → 新しいコラーゲン線維の形成促進
-
再配列 → 正常な張力ラインに沿ったコラーゲン構造
マニュピレーションの実施後の反応
🌀 治療後の反応プロセス
-
~10分後:局所の腫れや痛み増加(炎症反応開始)
-
数時間後:好中球 → マクロファージ → 線維芽細胞が活性化
-
1~3日後:一時的な症状悪化や小血腫
-
5日後~:局所の痛み軽減
-
20日間:Ⅲ型 → Ⅰ型コラーゲンへリモデリング
📅 治療頻度の推奨
-
週1回 × 2~3回 → その後1ヶ月の休止期間
※コラーゲンの再配列に約20日間かかるため
なぜ「一点治療」ではダメなのか?
筋膜は身体全体で張力のバランスを取っています。痛む場所=本当の原因とは限らないため、
「なぜそこに負荷が集中したのか」
「どの筋膜ラインが代償しているのか」
といった全体像の把握と評価が何より重要になります。
|
|



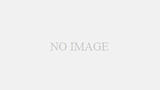
コメント