「栄養バランスが大事」とよく言われますが、なぜ大事なのか?
それをしっかり理解している人は意外と少ないかもしれません。
今回は『きちんとわかる栄養学』(飯田薫子・寺本あい)から、健康と栄養の基本をわかりやすくまとめました。
これを読めば、日々の食事の「意味」がぐっとクリアになります。
🥗 栄養学の基本 ― 三大・五大・第六の栄養素
まず覚えておきたいのが「三大栄養素」。
-
炭水化物:体や脳を動かすエネルギー源。不足すると疲れやすく、集中力も低下。
-
タンパク質:筋肉・内臓・皮膚・血液など体の材料。人体の約20%を構成。
-
脂質:エネルギー源としてだけでなく、細胞膜やホルモンの材料にもなる。
ここに ビタミン・ミネラル を加えた「五大栄養素」。
さらに近年では「食物繊維」も重要視され、「第六の栄養素」と呼ばれています。
👉 三大栄養素を上手に働かせるには、ビタミン・ミネラルが不可欠!
🔥 エネルギーの基本 ― カロリーと基礎代謝
1日の消費エネルギーの内訳は、
-
基礎代謝:約60%
-
身体活動:約30%
-
食事による熱産生:約10%
三大栄養素のエネルギー量は以下の通り:
| 栄養素 | 1gあたりのカロリー |
|---|---|
| 炭水化物 | 4 kcal |
| タンパク質 | 4 kcal |
| 脂質 | 9 kcal |
🍞 炭水化物と糖の話 ― 「無糖」でも糖がある?
炭水化物は「糖質」と「食物繊維」に分けられます。
食品表示では「糖質ゼロ」「糖類ゼロ」と書かれていても、100g中0.5g未満なら“ゼロ”と表示できるというルール。
つまり、“ゼロ”でも実際は少量の糖が含まれている場合もあります。
🍳 卵とコレステロールの新常識
「卵は1日1個まで」というのは昔の話。
食事でとるコレステロールと血中コレステロール値はあまり関係がないことがわかってきました。
コレステロールの多くは肝臓で合成され、食事の摂取量が増えると合成が減り、逆に減ると合成が増える――つまり体が調整してくれる仕組みがあります。
🫒 脂質と油の選び方
油は「悪者」ではなく、バランスが大切。
-
飽和脂肪酸(肉・バターなど):摂りすぎ注意。
-
不飽和脂肪酸(魚・植物油など):血中脂質を整える働き。
理想の比率は
飽和脂肪酸:一価不飽和脂肪酸:多価不飽和脂肪酸=3:4:3
また、不飽和脂肪酸にも摂りすぎ注意のものがあるため、さまざまな油をバランスよく摂ることが大切です。
🥕 野菜のとり方 ― 緑黄色と淡色のバランス
1日の目標は 野菜350g以上。
そのうち 120g以上を緑黄色野菜 に。
緑黄色野菜:βカロテン、ビタミンA
淡色野菜:ビタミンC、食物繊維が豊富
どちらも欠かせません!
🍲 生と加熱、どっちがいい?
| 生のメリット | 加熱のメリット |
|---|---|
| 栄養素の損失が少ない | 量を多く食べられる・殺菌効果 |
| 満腹感を得やすい | 消化吸収が良くなる |
加熱でビタミンが流出する場合は、スープにすれば無駄なく摂取可能!
🌾 食物繊維 ― 第6の栄養素
食物繊維は消化されませんが、腸内で大活躍!
-
不溶性食物繊維(穀類・野菜・豆類):便通を促す
-
水溶性食物繊維(海藻・果物・こんにゃく):コレステロールや血糖値の上昇を防ぐ
便秘、糖尿病、動脈硬化の予防にも◎
💧 水分の重要性
体の約60%は水。
体温の維持、代謝、老廃物の排出などに欠かせません。
1日に必要な水分量は約2〜3L。
飲み物だけでなく、食事からも約1Lの水分が摂れます。
🍚 朝食抜きはNG?代謝と肥満リスク
朝食を抜くと、
-
代謝が始まらず消費エネルギーが減少
-
昼・夜の血糖値が上がりやすく肥満リスク増加
-
体温上昇が遅れてエネルギー消費が抑えられる
👉 朝食は「体内時計」と「代謝」をスタートさせるスイッチ!
⚖️ 体重と肥満 ― BMIで確認
| BMI | 判定 |
|---|---|
| 18.5未満 | 低体重 |
| 18.5〜25 | 普通体重 |
| 25〜30 | 肥満(1度) |
| 30〜40 | 肥満(2〜3度) |
| 40以上 | 肥満(4度) |
理想のBMIは22(病気が最も少ない数値)。
🌿 ファイトケミカルと抗酸化作用
野菜や果物に含まれる「植物の力」。
代表的なもの:
-
ポリフェノール
-
カロテノイド
-
イオウ化合物
これらはすべて抗酸化作用を持ち、細胞の老化や生活習慣病を防ぎます。
🦠 腸内フローラと発酵食品
腸内には100兆個以上の菌が存在。
理想のバランスは
善玉菌:悪玉菌:日和見菌=2:1:7
発酵食品(ヨーグルト、納豆、味噌など)で善玉菌を増やすことが、腸内環境を整えるカギ。
乱れると便秘・免疫低下・肥満・うつなど様々な不調に。
🍱 栄養バランスを整える4つのポイント
-
彩りで考える(見た目に色が多いと栄養も多い)
-
一汁三菜を意識
-
6つの食品群を意識
-
日本人の食事摂取基準を参考に
特定の栄養素よりも「全体のバランス」が大切。
🧂 食塩を減らすコツ
日本人は平均10g/日と摂りすぎ傾向。
理想は 6g未満(WHOは5g未満)。
味に深みを出す工夫で減塩:
-
酸味(レモン・酢)
-
香り(ハーブ・生姜)
-
うまみ(出汁)
-
香ばしさ(焼き目)
-
とろみ(片栗粉など)
🍵 健康食品は「補助的に」
サプリや健康食品は、あくまで「サポート役」。
本当に健康を作るのは、毎日の食事・睡眠・運動の積み重ねです。
✨ まとめ
-
栄養は単体では働かない。
-
食事は「バランス」と「継続」が最重要。
-
特定の食材や健康法に偏らず、“いろいろ食べる”が最強の健康法。
🩺 理学療法士・運動指導者の視点から
身体を動かすにも、栄養が足りなければ回復も筋肉づくりも進みません。
トレーニングもリハビリも、「栄養」があってこそ最大限の効果が発揮されます。

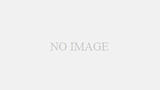
コメント